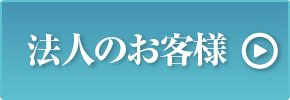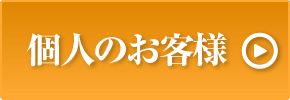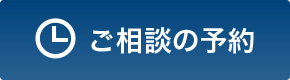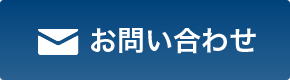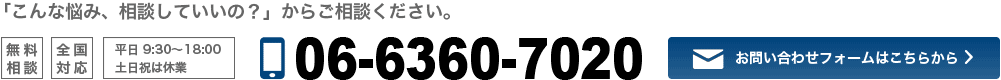Q.利息制限法とはどのような法律ですか?
利息制限法とは、借入金の利息の上限を規定した法律であり、利息制限法で規定する利率を超える利息(これを制限超過利息といいます)に関する合意は無効となります。
Q.グレーゾーン金利とは何ですか?
グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の間の金利部分のことです。
出資法の上限金利を超えると刑事罰が科せられますが,利息制限法の上限金利を超えても刑事罰はなく、民事上無効となるだけです。この民事と刑事の金利の差がグレーゾーン金利と言われています。
グレーゾーン金利の利息は、みなし弁済が認められない限り無効ですので、債務整理を行えば、払いすぎの利息として、元本に充てられることになります。
これがいわゆる利息制限法に基づく引直計算であり、これにより借金の減額が可能となるのです。
また取引期間が長い場合、払いすぎた利息を元本に充当していくと最終的には元本もなくなります。
この場合になお払いすぎて残っている部分の金額が過払いとなります。
Q.過払金が発生している場合には、どのように返還してもらうのですか?
引直計算により過払金の発生が明らかとなった場合、まず、貸金業者に対して過払金を返還するよう任意の交渉を行います。
過払金全額の返還を拒んだり、支払日を半年以上先にするなど、任意の交渉では解決が難しい場合には、訴訟を提起して過払金返還請求を行うことになります。
Q.弁護士に依頼せず個人で過払金返還請求をすることはできますか?
弁護士に依頼せず、個人であっても、貸金業者に対して、取引履歴を請求し過払金を請求することができます。
ただし、貸金業者の中には、個人の場合には大幅な減額を提示するなど、貸金業者のペースですすめられることもあるため、個人で行う手間なども考えると、弁護士に依頼することをお勧めします。
Q.過払金はどの程度返ってきますか?
業者によって異なります。
当事務所では、原則として、支払過ぎた金額の全額回収を目標としております。
Q.完済している業者に対しても請求できますか?
過払金の請求は業者との契約に基づいて請求するものではないので、完済しているかどうかは関係ありません。
利息制限法を超える金利で支払を続けて完済している場合には,過払金は必ず発生しています。
過払金は取引が終了した日から10年間は時効にかかりませんので、完済している業者こそ、過払金の返還請求をするべきです。
Q.貸金業者が取引履歴を一部しか開示しない場合、引直計算はどのようにすればよいですか?
貸金業者の中には、10年以上前の取引履歴の開示に応じない業者や、借り換えや完済などによる取引の中断があると、それ以前の取引履歴の開示をしない業者があります。
この場合、貸金業者は開示した取引履歴の冒頭残高をそのまま貸付額として引直計算することを主張してくることが考えられます。 しかし、それ以前に超過利息の取引が継続していた場合、引直計算すると開示された冒頭残高よりも残高が少なくなることは明らかであり、貸金業者の主張は到底受け入れられるものではありません。
しかし、それ以前に超過利息の取引が継続していた場合、引直計算すると開示された冒頭残高よりも残高が少なくなることは明らかであり、貸金業者の主張は到底受け入れられるものではありません。
そこで、貸金業者が取引履歴を一部しか開示しない場合、借主の方に振込や返済が分かる通帳や領収書等の資料があれば、それをもとに取引履歴を推定し、引直計算をすることになります。これを推定計算といいます。
全く手元に資料がない場合、記憶を頼りに取引履歴を推定することになります。
また、取引履歴を証明する責任は貸金業者側にあり、借主側は開示された部分だけを証明すれば良いという見解から、開示された取引履歴の冒頭残高を0円として推定計算をする方法もあります。
いずれにしても、全ての取引履歴が開示され引直計算をすれば、残高が減ることは確実なので、安易に貸金業者の主張に従わないように注意すべきでしょう。
Q.途中で完済していますが、その後の取引も通算して引直計算できますか?
取引履歴が複数の取引に別れている場合、それが全くの別取引であれば別々に引直計算をすることになります。
しかし、形式的には一度完済しているが、実際は単なる借換えに過ぎないような場合や、完済から再取引までの期間が短い場合など、実質的には一つの連続した取引と見られる場合には、引直計算も一つの取引として行うべきです。
実質的に一つの連続した取引といえるか否かは、次の1.〜7.の要素から判断されています。
- 第1の基本契約に基づく貸付及び弁済が反復継続して行われた期間の長さ
- 最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間
- 第1の基本契約についての契約書の返還の有無
- 借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無
- 第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況
- 第2の基本契約が締結されるに至る経緯
- 第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同
Q.みなし弁済ってどういうものですか?
みなし弁済とは、旧貸金業法43条1項に定められていたものであり、債務者が任意に利息を支払った場合には、本来無効であるはずの利息制限法を超えた利息が一定の要件の下、有効になるというものです。
現在はみなし弁済の規定は廃止されており、現在の取引について、みなし弁済が成立する余地はありません。
また、みなし弁済の要件は厳格に解釈されているため、過去の取引についても、みなし弁済の成立が認められるのは極めて稀なこととなっています。
Q.過払金に利息はつきますか?
過払金返還請求権は、法律上は不当利得返還請求権であり、過払金発生時から年5%の利息が付きます。
貸金業者は過払金について民法704条の悪意の受益者に該当すると考えられるからです。
貸金業者は、悪意の受益者には該当しないとして、過払金の利息の返還を拒むことが多いですが、多くの裁判例において、貸金業者は悪意の受益者に該当するとして過払金発生時から年5%の利息の返還義務を認めています。
Q.10年以上前に一度完済して、その後また取引を再開しました。10年以上前の取引の時に発生した過払金は請求できますか?
過払金返還請求権は、取引が終了した時点から10年間が経過すると時効により消滅します。
しかし、10年以上前に完済している場合でも、その後に取引を再開している場合には、次の1.〜7.に照らして、一個の連続した取引といえる場合には、再開後の取引(第2取引)が終了してから10年間が経過するまでは、以前の取引(第1取引)で発生していた過払金返還請求権も消滅せずに請求できます。
- 第1の基本契約に基づく貸付及び弁済が反復継続して行われた期間の長さ
- 最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間
- 第1の基本契約についての契約書の返還の有無
- 借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無
- 第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況
- 第2の基本契約が締結されるに至る経緯
- 第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同