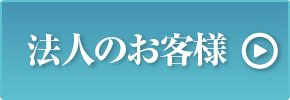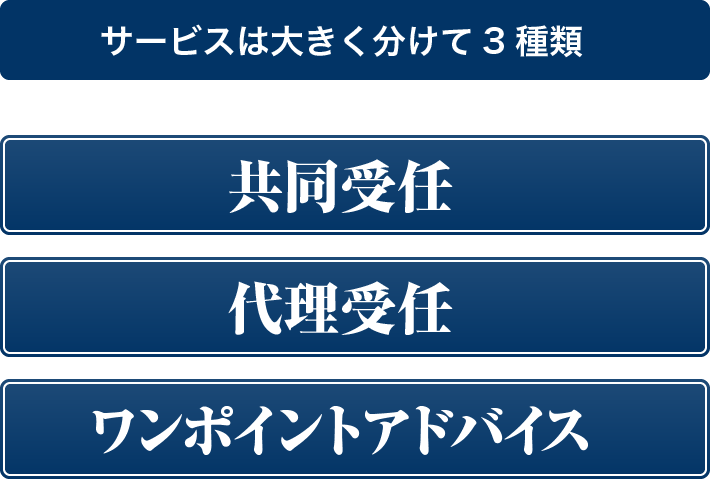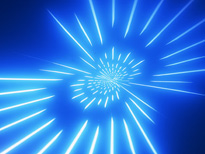 従業員が職務上行った創作の成果の帰属は、発明と著作物法によって大きくことなります。なお、考案、意匠については特許法が準用され発明と同じ取扱いとなります。
従業員が職務上行った創作の成果の帰属は、発明と著作物法によって大きくことなります。なお、考案、意匠については特許法が準用され発明と同じ取扱いとなります。
職務著作については使用者が著作者となり著作権帰属者となります(著作権法15条)が、職務発明については実際に発明を行った従業員に特許を受ける権利が帰属します(特許法35条)。
この結果、使用者が職務発明に関する特許権を得るためには、予め、あるいは、職務発明がなされた後に、発明者から「特許を受ける権利」を譲受ける必要があります。
但し、使用者が発明者である従業員から、「特許を受ける権利」を譲受けた場合、当該従業員に対して「相当の対価」の支払いを行う必要があります。
平成16年改正以前は「相当対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。」とのみ規定されていました。
そして、東京地判平14・1・30「青色発光ダイオード事件」(平成13年(ワ)第17772号)において200億円の支払いを命じる判決が下され、使用者である企業としては、相当対価の支払が経営リスクとして認識されるようになり、特許法35条の改正が強く望まれるようになりました。
当時においても、特許法35条については職務発明が原始的に使用者に帰属する内容への改正が求められていましたが、従業員の権利保護、従業員発明の奨励等の観点から、職務発明が発明者である従業員に帰属するという制度を維持した上で、使用者である企業に予見性を高める内容への改正が行われました。
平成16年改正によって、職務発明の相当対価の額の決定は、その金額の妥当性もさることながら、職務発明規定の策定から規定上の対価決定、現実に支払われる対価の決定手続において対価が支払われる対象となる従業員の関与が十分に行われているかという点が重視されるようになりました。
使用者である企業としては、現行特許法35条の趣旨を理解した上で、事前の対応をとっておくことにより、相当対価の支払いが経営リスクとなることを回避することが可能となりました。
ところが、特許庁等の調査によると、現在においても、多くの企業において現行法に沿った形で職務発明規定が整備されていない状況にあるとされています。
そして、かかる状況を受けて、政府は、職務発明の相当対価に関する規定の義務付けを検討しています。
そこで、今一度、特許法における職務発明規定の内容を、特許庁が作成した「新職務発明制度における手続事例集」を参考に概観します。