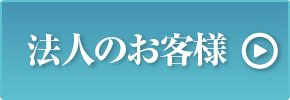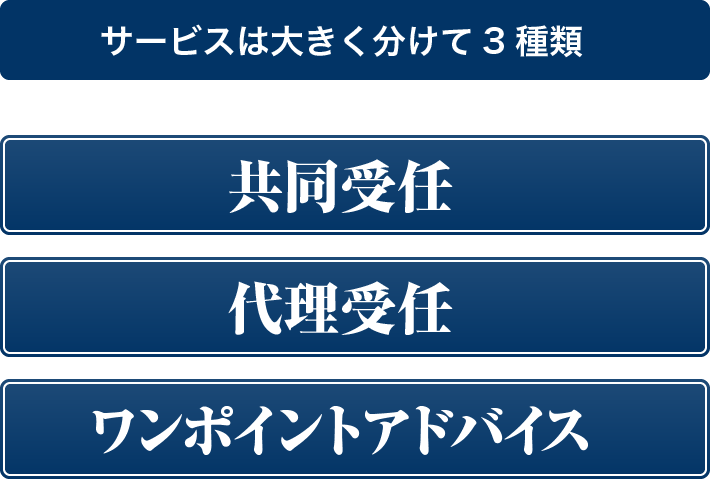知的財産法では損害額が推定される
各知的財産法では、損害額の推定規定が設けられています。
いずれの法律も同様の規定をもうけていますので、本稿では特許法を例に説明します。
概要
 特許法は、特許権者が被った損害額の推定規定として以下の3つのものを設けています(102条)。
特許法は、特許権者が被った損害額の推定規定として以下の3つのものを設けています(102条)。
- 1項:侵害者が譲渡した物品の数量に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額。ただし、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を上限とする。
- 2項:侵害者が、侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額。
- 3項:特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額
1項
本項は、平成10年特許法改正により新設された規定です。
旧102条1項(現102条2項)は、特許権者による特許権の実施が必要であると解されているところ、特許権者が特許権を実施していない場合には、旧102条2項(現102条3項に対応)により損害額が推定されることになりました。
ところが、同項の推定損害額は、特許権者に実施許諾を求めた際に支払うことになる実施許諾料と同程度と解されていました。
この結果、実施されていない特許権については、予め実施許諾契約を締結して実施許諾料を支払うよりも、侵害行為が発覚した際に実施許諾料を支払った方が得であるとの判断に至り侵害行為を誘発するとの批判がありました。
また、特許権者が特許権を実施している場合であっても、侵害者が特許権侵害により利益を得ていない場合や廉価販売を行っているために利益が小額に留まる場合には、特許権者の逸失利益の填補としての機能を果たせないという問題がありました。
そこで、設けられたのが現102条1項です。本項は、特許権は第三者に特許権を実施することを認めない権利であるところ、侵害の行為を組成した物を譲渡することができる場合においては、侵害者の譲渡数量は権利者が喪失した販売数量であるとの推定が成り立つということを前提としています。
そこで、侵害者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、以下の式により算出された金額を特許権者が被った損害であると推定されます。
推定損害額=「侵害者が譲渡した物品の数量」×「侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額」
侵害の行為がなければ販売することができた物品
「侵害の行為がなければ販売することができた物品」とは、侵害品と代替可能な物品で、かつ、特許権者において販売することができた物品のことをいいます。
ここで、侵害品との代替可能性については争いがあり、完全な代替性まで必要ではなく、侵害品の需要が少しでも特許権実施品に向かう性質のものであれば足りると解する見解と、侵害品が特許発明の実施品であることを要するという見解があります。
侵害品の需要が少しでも特許権実施品に向かう性質のものであれば足りるとする見解は、競合する製品であれば侵害と損害との因果関係が認められる場合があること、完全な代替性を求めていくと本項を新設した意義が失われることを理由とします。
他方、完全な代替性を求める見解は、権利者の実施品が特許発明の実施でないとすれば、そのような製品は侵害品と性能・効用において同一製品と評価することができず、また権利者以外の第三者も自由に販売することができるのであるから、市場において侵害品と同等の物として補完関係に立つということができないことを理由としています。
「蓄熱材製造方法事件」判決(東京高裁平成11年6月15日判決)では、特許権者が侵害品と競合する製品を販売し、全国各地で侵害品競合して受注競争をしていることをもって「侵害の行為がなければ販売することができた物品」と判断しており前者の考え方に立脚すると理解されています。
他方、「生海苔異物分離除去装置事件」判決(東京地裁平成14年4月25日判決)では前記した理由により後者の考え方に立脚しています。
そもそも、本項は、特許権者が特許権を実施していない場合の損害賠償が十分に図れないという経緯で制定された規定であるにもかかわらず、特許権者が特許権を実施していることを前提とした完全な代替性を求める解釈は、本項の制定経緯を無視した解釈という他ありません。
よって、「侵害の行為がなければ販売することができた物品」とは、侵害品の需要が少しでも特許権実施品に向かう性質のものであれば足りると解すべきです。
ただし、本項は、特許権者による特許権不実施の場合にも適用されるものの、「販売することができた」と規定している以上、特許権者において特許権実施の予定が全くない場合には、適用されないと解さざるをえません。
以上より、「侵害の行為がなければ販売することができた物品」とは、特許権者において販売する予定であるもので、侵害品の需要が少しでも特許権実施品に向かう性質のものと解することになると考えます。
侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益
本条1項では「単位数量当たりの利益」という文言が存在しますが、特許法には「利益」に関する定義規定が存在しません。そこで、本条による損害額の推定にあたっては、本条にいうところの「利益」とは何を指すのかが問題となります。
「利益」とは、「売上」から「経費」を差引いた金額を指す概念ですが、ここで差引くべき「経費」をどの範囲で認めるのかが問題となるのです。
そもそも、本項は、特許権者が特許権侵害による売上減少により喪失した逸失利益を立証できない場合においても合理的な範囲でそれを逸失利益と推定し、損害賠償制度の実をあげ、もって特許権者の保護を図る規定です。
そして、本項は、侵害者の譲渡数量が権利者の喪失販売数量であるとの推定に基づいています。
このような本条の趣旨を前提とする限り、「売上」から差引くべき「経費」は、侵害者が販売した個数の製品を特許権者において製造・販売する場合に要することになる追加費用ということになります。
例えば、特許権者において、新たな生産手段を設ける必要がない場合においては生産設備を整えるのに要する費用は差引くべき費用に含まれません。
また、特許権者において新たな従業員を雇用する必要がない場合においては人件費もこれに含まれません。
他方、追加生産するのように要する原材料費、追加販売するのに要することになる販売費用については「経費」に含めることになります。
つまり、「単位数量当たりの利益」とは、侵害がなければ増加すると想定される代替品の単位当たり売上額から、侵害がなければ増加すると想定される代替品の単位当たりに割り付け控除した額をいいます。
このような利益は限界利益と呼ばれ、上記のような考え方を限界利益説といいます。
特許権者が自己の製品を製造販売するために必要な初期投資を終えた後に得られる製品1個当たりの利益であり、売上から追加の製造販売を行うのに必要な経費を控除した利益ということになります。
前記「蓄熱材製造方法事件」判決では、特許権者の製品1m2当たりの売上から、それを達成するために増加すると想定される費用を1m2当たりに割付けて控除した額の平均をもって権利者製品の1m2当たりの利益の額と認定されています。
また、「記録紙事件」判決(東京地判平成13年7月17日判決)、「溶接用エンドタブ事件」判決(東京高判平成15年10月29日)、「病理組織検査標本作成用トレイ事件」判決(大阪地判平成17年2月10日等、多数の裁判例で限界利益説が採用されています。
特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を上限とする
「侵害者が譲渡した物品の数量」に「侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額」を乗じた金額が、特許権者の実施の能力を超える場合には、実施能力に応じた額に減じられることになります。この結果、そもそも生産能力を有していない部分等は損害推定額から控除されることになります。
当該規定は、本項が懲罰的損害賠償を認めたものや特許権侵害の抑制を主たる目的とするのではなく、あくまで特許権者の逸失利益の賠償を目的としたもので、侵害行為と損害との因果関係を求める伝統的な損害論に立脚していることを示すものといえます。
ただし、特許権者の実施能力を抽象的にとらえた場合には、実質的に当該規定の制限が働かなくなり、侵害行為とは因果関係のない範囲の損害まで賠償することを意味することになります。
前記「溶接用エンドタブ事件」判決では、「金融機関等から融資を受けて設備投資を行うなどして、当該特許権の存続期間内に一定量の製品の製造、販売を行う潜在的能力を備えている場合には、原則として『実施の能力』を有するものと解することが相当である。」等、多くの裁判例で同様の考え方が採用されています。
上記裁判例のように抽象的な可能性でも実施能力があると認められるとすると、結論の当否は別として当該規定により上限額を設けた法の趣旨は没却されます。
単に予定があるだけで実施能力があると認めることはできず、具体的な自社工場や製造委託先の工場の規模等を考慮して、製造余力がある場合等に実施能力があると認めるべきであると考えます。
譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者が販売することができないとする事情
特許権侵害者の営業努力、市場開発努力によって販売が可能となったこと、市場において侵害品以外の代替品や競合品が存在すること、侵害者の価格設定が購入が集中したこと、明らかに侵害品の方が性能が優れていること、特許製品と侵害品との販売方法に大きな違いが存在すること等が、これにあたります。
特許権者が販売することができないとする事情は、特許権者において主張・立証する必要があります。
なお、抽象的な主張では足りず、特許権者が販売することができない事情を具体的に主張し、これを立証する必要があります。
そして、権利者が販売することができない事情が認められると、「侵害者が譲渡した物品の数量」に「侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額」を乗じた金額(ただし、特許権者の実施能力を上限する。)から、当該割合相当分が控除されることになります。
前記「蓄熱材製造方法事件」判決では、市場占有率が、特許権者35%、侵害者35%、その他の企業30%の場合に、侵害者の譲渡数量の内75分の30については侵害行為がなくとも特許権者が販売することができなっかったとして「特許権者が販売することができない事情」が存在すると判断され、特許権者が販売できないと認定された数量については102条3項が適用され5.26%の実施料相当損害金が認められています。
また、「パチスロ事件」判決(東京地裁平成14年3月19日判決)では、「侵害品と権利者製品が市場において補完関係に立つという擬制の下に設けられた規定である。」と判示し、との点を強調し、「侵害者の営業努力や、市場に侵害品以外の代替品や競合品が存在したことなどをもって、同項ただし書にいう『販売することができないとする事情』に該当すると解することができない。」と判示され、東京高裁平成11年6月15日判決、東京地裁平成12年6月23日判決、東京高裁H14年10月31日判決では、市場に権利者・侵害者以外の第三者の競合品が存在する場合に、その分は権利者が販売することができないとする事情になると判示され、東京高裁平成12年4月27日判決では、通常実施権者の競合品が存在する場合に、当該競合品の販売分は権利者において販売することができないとする事情があったものとすると判示されています。
さらに、大阪地裁平成17年2月10日判決では、侵害品の大部分が無償譲渡であったことや競合品の存在により、侵害品の約半数が権利者が販売することができないとする事情があったと判示され、大阪高裁平成14年4月10日では、著しい販売格差や代替品の存在を理由に侵害品の7割を販売することができないとする事情があったと判示されています。
ところで、権利者が販売することができないとして控除された部分についても、特許権侵害にあたり実施許諾がない限り製造することが認められていません。
そこで、控除された部分については102条3項を適用して賠償額が算定され、特許権者に対する賠償金額に加算されることになります(大阪高裁平成14年4月10日判決、東京高裁平成11年6月15日判決、東京地裁平成12年6月23日判決、大阪地裁平成17年2月10日判決参照)。