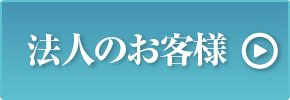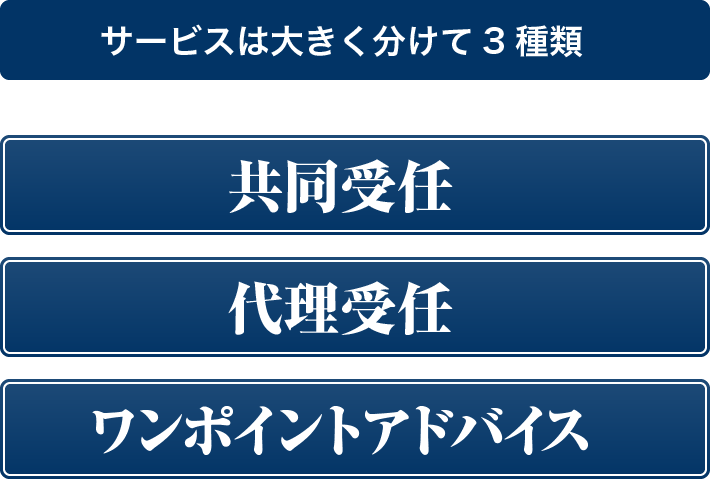意匠の類否判断を検討する前提として,まず,意匠権が異なる物品に対しても権利が及ぶのか否かを考える必要があります。
仮に意匠権が異なる物品に対しても及ぶということになれば意匠と物品とは可分の関係になりますし,意匠権が異なる物品に対して及ばないということになると意匠と物品とは不可分の関係にということになります。
例えで説明しますと,乗り物である飛行機の形状があり,それが意匠登録されている場合に同一の形状のおもちゃに対しても意匠権の効力が及ぶのかという問題として考えると理解が容易ではないでしょうか。
卑近な例で説明すると,日本の意匠制度において,飛行機の形状が意匠登録されている場合に精巧なおもちゃを製造すると意匠権を侵害すると考えるのか否かということになります。
多くの書物では,意匠法における意匠の定義が「物品の形状,模様,若しくは色彩又はこれらの結合であって・・・」と定義されており,物品「の」と規定されているため,意匠と物品は一体であり,異なる物品に意匠権が及ばないと説明されていることがあります。
しかし,日本語の「の」という言葉の意味は非常に多義的で,「の」と規定されていることが,当然に物品と意匠が一体であることを明示していると解釈することはできないと考えています。
そこで,意匠法の沿革との関係で検討することにします。
日本の意匠法は,明治21年に意匠条例という形で導入されました。
この意匠条例は,英国法の影響を受けており,意匠は物品に「応用すべきもの」と規定されており,物品とは無関係に,形態の類否判断のみが行われていました。
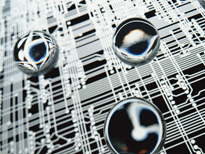 そして,明治42年に意匠法が制定されるわけですが,明治42年法においても,意匠は物品に「応用すべきもの」のと規定されており,意匠権を登録するにあたり権利を及ぼす物品の範囲指定する類別指定制度というものが設けられていました。
そして,明治42年に意匠法が制定されるわけですが,明治42年法においても,意匠は物品に「応用すべきもの」のと規定されており,意匠権を登録するにあたり権利を及ぼす物品の範囲指定する類別指定制度というものが設けられていました。
商標の指定商品,指定役務と同様の制度であると考えれば,容易に理解できるのではないでしょうか。
また,明治42年法では,意匠権は,登録した物品ごとに個別に譲渡することができるというものでした。
明治21年法,明治42年法は,意匠と物品は可分な関係にあることを前提にしており,明治21年法では異なる物品に対しても意匠権が及び,明治42年法では登録時に指定した物品に限定されているものの,異なる物品に対して効力が及ぶという制度でした。
大正10年に意匠法の改正が行われ,意匠は物品に「関するもの」と規定されるようになりました。
この「関するもの」という日本語も実に多義的あり,この文言からだけで意匠と物品との関係を判断することはできません。
ところが,大正10年法は,明治42年法の制度を引継ぎ,類別指定制度を採用し,複数の異なる物品を指定して意匠登録することが認められ,物品ごとの分割譲渡も認められていました。
この制度を見る限り,大正10年法においても明治42年法と同様に,意匠と物品は可分な関係にあると考えられなくはありません。
ところが,大正10年法では,指定物品と同一の物品についての登録意匠に類似する意匠の応用が意匠権の侵害であると規定されていました。
大正10年法を前提にする限り,意匠と物品とは可分な関係であるが,意匠制度としては権利範囲同一の物品に限定する,すなわち制度的には不可分なものとするという制度を採用していたと理解すべきであると考えています。
以上のように,意匠法を沿革的にみると,意匠と物品との関係は一義的なものではなく,むしろ意匠と物品とは理論的には可分な関係にあるが,制度として異なる物品に意匠権を及ぼすことが適切ではないとの理由により一体のものとして取り扱っていたと理解すべきなのです。
現行法の意匠権の範囲に関する規定は,単に「業として登録意匠及びこれに類似する意匠」に対して権利が及ぶとのみ規定されており,大正10年法のような物品との関係で意匠権が及ぶ範囲に関する規定は存在しません。
現在の意匠法の基礎は大正10年法にあるところ,現行法は,理論的に意匠と物品とが可分の関係にあることを前提として,物品との関係で権利の範囲を限定する規定も存在しないことから,異なる物品に対しても意匠権が及ぶと解釈することもできます。
むしろ,沿革的にみた場合には,現行法においても,意匠権は異なる物品に対しても及ぶと考えるべきであると言ってもよいと思います。
 ところが,意匠と物品とは一体であることを前提に実務が運用されていますし,裁判例や判例においては,理由を示すことなく「意匠と物品は一体であるから,意匠の類否判断においては物品の類否判断を行う必要がある」という趣旨の判示がなされることが少なくありません。
ところが,意匠と物品とは一体であることを前提に実務が運用されていますし,裁判例や判例においては,理由を示すことなく「意匠と物品は一体であるから,意匠の類否判断においては物品の類否判断を行う必要がある」という趣旨の判示がなされることが少なくありません。
意匠と物品を一体のものとして取扱う法的根拠としては,裁判例や判例ということになるのでしょうが,その裁判例や判例において,なぜ意匠と物品が一体であるのかを明らかにしたものがありません。
沿革的にみた場合にはむしろ可分の関係にあると思える意匠と物品との関係ですが,なぜ一体のものとして理解すべきということになるのでしょうか。
それは,意匠法における意匠の本質から考察した場合に意匠と物品とは不可分と考えざるを得ないからであるということになると考えています。
では,意匠の本質とは何なのでしょうか。
意匠法の「意匠」とは,「物品の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であって,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。」と定義されています。
この定義と類似する定義が不正競争防止法で定められている「商品形態」です。
不正競争防止法上の「商品形態」とは,「需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様,色彩,光沢及び質感をいう。」と定義されています。
「意匠」の定義においては「通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる」という限定が存在しませんが,裁判例においては,「視覚を通じて」という要件が存在することにより,分解したり,破壊しなければ確認できない,つまり通常の使用方法により視認することができない部分は意匠の構成要素とはならないと解されているため,この点に関する限り,意匠と商品形態との間に差はありません。
視覚と知覚についても,用語は異なるものの人の五感において同一のものを指しているという点で差異がありません。
商品と物品についても用語は異なるものの,商品と製品との差程度に理解しておいて問題がありません。
さらに,商品形態については,意匠にはない「光沢」や「質感」が要件に含まれていますが,意匠は図面や写真,ひな形,見本によって意匠を特定する方法で登録を行うため市場で流通している物品に備わる光沢や質感が問題にならないのに対し,商品形態は,まさしく市場で流通している現実の商品が問題となるため「光沢」や「質感」が問題となるのであって,意匠と商品との決定的な差異にはならないと考えています。
「意匠」と「商品形態」の決定的な差異は,「意匠」が単なる「物品の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合」(商品形態でいうところの「商品の形状並びにその形状に結合した模様,色彩」)に留まらず「視覚を通じて美感を起こさせるもの」という要件が加わっているところです。
すなわち,意匠と,単なる物品(商品)の形状,模様,色彩又はこれらの結合との決定的な差異は「視覚を通じて美感」の有無であり,ここに意匠の本質が存在するのだと考えています。
それでは,意匠法がいうところの「美感」とは一体何なのでしょうか。
これを考えるにあたっては,物品(商品)の形態がどのように決定されるのかということを考える必要があります。
推進力を利用して空を飛行する乗物(飛行機)を製造しようとするとき,洋上を航行する船舶の形状の乗物を製造することはありません。
また,逆に,洋上を航行する乗物を製造しようとするときに,推進力を利用して飛行する飛行機の形状の乗物を製造することはありません。
これは,当然のことではありますが,物品(商品)を製造する際に,その物品(商品)が果たす機能によって必然的に決定される形状というものが存在するのです。
物品(商品)の機能を最大限発揮させることのみを考慮して決定される物品(商品)の形状というものが存在しますが,その物品(商品)には色彩や模様が伴うのが一般的です。素材の色彩をそのまま生かしたものであったとしても,他の色彩を施さないという意味で物品(商品)の色彩を決定していることになります。
それは,他の機能のみを追求した物品(商品)との関係で市場での競争力を獲得するために行われるのです。
また,機能を追求したことにより生み出された形状に,機能を大きく損なわない範囲で形状的な装飾が施されることがあります。このようなことを行う理由も,他の物品(商品)と区別して市場での競争力を獲得するために行われます。
加えて,色彩や模様についても,加えて市場での競争力を獲得するために行われることもあるでしょう。
他方,物品(商品)の形状というものは,需要者の観点からだけではなく,それに加えて製造や運送のコストを考えて決定されることもありますし,物品(商品)の耐久性を考慮して決定されることもありますし,その他様々な要因が複雑に絡まり合って特定の物品(商品)の形状が最終的に決定されていきます。
物品(商品)の形態は,基本的には物品(商品)の機能により決定づけられるのですが,それをベースに製造,流通の過程を経て需要者の手に届くまでの様々に要請から生まれる形態への要求を加味して,一つの物品(商品)に秩序立てて表現する上での形態的な秩序が意匠法でいうところの「美感」であると考えています。
意匠の本質である「美感」を以上のものであると考えた場合,意匠が現実に存在する物品と可分なものとして存在しえません。
ですから,意匠と物品とは一体の関係にあるということになるのです。
意匠と物品が一体の関係にある場合,意匠法によって特別な定めがない限り,異なる物品については異なる意匠ということになります。表現を代えるならば,意匠権は異なる物品に対しては及ばないということになるのです。
ですから,意匠の類否判断,意匠権の効力が及ぶ範囲を検討するにあたっては,物品の異同ということが問題になるのです。