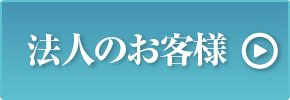現在の特許法では,従業員が職務上行った発明(職務発明)については,従業員が特許を受ける権利を有するとされています。従業員が職務上行った著作物の創作については,著作者が法人とされ,法人が著作権(人格権,財産権ともに)を有するのとは全くことなります。
例えば,プログラムは,著作物でありながら,新規性,進歩性を有するものであれば特許発明として登録することができますが,特許として登録しなければ法人に,特許として登録しようとすれば従業員から特許を受ける権利を取得する必要があることになり,法的結論の均衡がとれていません。
従業員に帰属する特許を受ける権利ですが,法人は,予め,就業規則等で特許受ける権利を承継する旨の規定を設けておけば,従業員の個別の同意を得ることなく特許を受ける権利を承継することができますが,承継を受けるにあたっては相当の対価を支払わなければなりません。
そして,相当対価の算定方法,対価の決定過程から対価が支払われるまで,対価を受けることとなる従業員などの関与が行われ,従業員などの意見が十分に反映されていなければ,結果的に成果報酬を支払わされるということになり,このことが企業にとって経営リスクとなっていました。
なお,一部の企業では,特許法35条4項に沿った職務発明規定を設けたり,相当対価の上限額を撤廃する等の対応を行うことで,日亜化学工業事件のようなリスクを回避しようとする動きもありますが,多くの企業では,職務発明に対する対応が十分ではないというのが現状です。
そこで,現在,政府の有識者会議では,一定の条件を満たせば、職務発明に関する特許を受ける権利を法人に帰属させる方向で検討が行われ,平成26年6月18日の有識者会議で意見の一致をみています。
また,同月20日の知的財産戦略本部の会合において,「知的財産推進計画2014」において職務発明の法人帰属を認める職務発明制度の見直しが盛り込まれており,早期に対応することが確認されています。
政府の有識者会議においては,来年の通常国会において特許法改正案を提出することが確認されていますが,どのような条件が整った場合に職務発明の法人帰属を認めるかについては非常に難しい調整が必要になります。
条件を厳しくすると、多くの企業が対応できなくなり特許法を改正する意味がなくなりますし,条件を緩くした場合には,従業員の発明に対する意欲が減退し,発明を促すことで経済の発展を実現するという特許法の目的が蔑しろにされるおそれもあります。
今後の政府の有識者会議における議論に注目する必要があります。