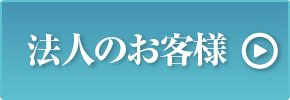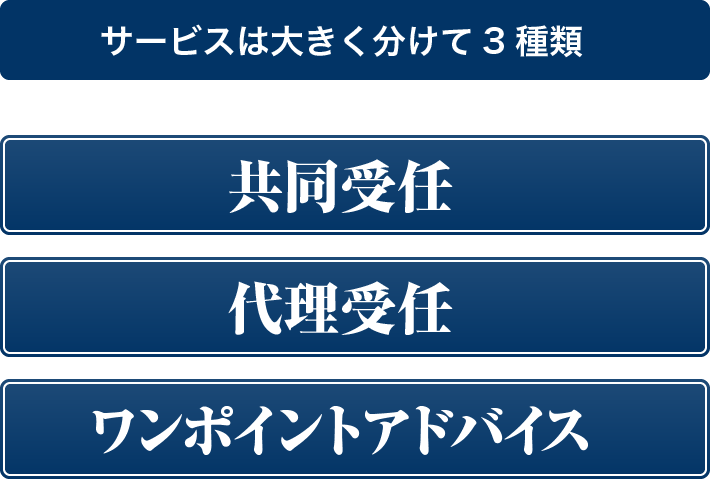2項
 本項は、特許権侵害により特許権者被った損害の立証が容易でないことを理由に、昭和34年特許法改正により創設されました。
本項は、特許権侵害により特許権者被った損害の立証が容易でないことを理由に、昭和34年特許法改正により創設されました。
なお、本項は、現行1項の創設により、2項に繰り下がりました。
本項は、侵害行為を原因とした販売減少による逸失利益の損害賠償請求において、侵害者の受けた利益の額を立証すれば当該利益の額を権利者の損害と推定するという規定です。
そして、本項は、損害の発生まで推定するのではなく、損害額を推定する規定であると解されており、特許権者が特許権を実施していない場合には、特許権実施により得べかりし利益が存在しないため本項適用の前提を欠くことになります。
そこで、本項は、特許権者が特許権を実施していることが前提になると解されています。
1項は、本項の規定が特許権者による特許権の実施に限定されると解釈を前提に、これによっては特許権者が侵害行為によって喪失した逸失利益の賠償としては十分ではないとの理由に設けられた規定です。
かかる立法経緯を前提とする限り、本項では特許権者が特許権実施品でないもの販売をしている場合には適用されないと解されています。
意匠権に基づく損害賠償請求事件に関するものですが、「包装用箱事件」判決(大阪地裁昭和59年5月31日判決では、「本項の損害額推定規定は、自らの権利を実施している権利者が侵害者の侵害によって蒙った消極的損害の額や因果関係を立証するのが極めて困難であることに鑑み権利者保護のために設けられた規定であって、単に権利を保有しているだけでこれを実施していない不実施権利者のようにもともと前示のような消極的損害の発生自体を観念することのできない者に適用すべき規定ではない」、「法は、このような場合、別途、当該権利の実施料相当額をもって権利者の蒙った損害とみるべき旨定めている。」と判示されています。
ただし、本項の規定を、侵害者による利益の吐き出しによる侵害行為の抑制にあるとして、特許権者による特許権の実施が不要であり、特許権者が特許権実施品の代替品を製造・販売している場合にも適用されるという見解があります。
侵害の行為により受けた利益の額
本項における利益の額は、1項と同様に限界利益と解されており侵害品の売上から、当該売上に対応する製造原価及び侵害行為により増加した販管費を差引いた額であると解されています。
推定の覆滅
本項は、前記したとおり侵害行為を原因とした販売減少による逸失利益の損害賠償請求を実現するための損害額推定規定に過ぎません。
よって、侵害行為によって特許権者が被った損害が侵害者が得た利益を下回る場合には、損害賠償額は、現に特許権者が被った損害の範囲に限定されることになります。
本項では、1項のように実施能力による制限について明定されていませんが、本項が損害額の推定規定であることから、当然のことと理解されています。
3項
本項は、特許権侵害により特許権者被った損害の立証が容易でないことを理由に、昭和34年改正により102条2項として新設され、平成10年改正で3項に繰り下がるとともに、「特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額」との規定から「通常の」という文言がが削除され現在に至っています。
昭和34年改正により新設される以前から、判例上、特許権者は、特許権侵害行為が存在すれば、侵害者が適法に実施したならば得べかりし実施料相当額を少なくとも喪失するという理由により、通常の実施料相当額を最低限の損害賠償として認められていました。そして、かかる判例理論を明文化したものが本項でした。
そして、旧102条2項では、「通常の」という文言が存在したため、最低限の損害賠償額ですら低額化する傾向があるとの批判があったため、平成10年改正により前記のとおり「通常の」という文言が削除されました。
実施許諾権を有すること
本項は、特許権者が特許権侵害行為によって被った損害額が、少なくとも実施料相当額であるとの推定の下に規定された損害額推定規定です。
ですから、特許権者が専用実施権を設定し実施許諾権を有しない場合には、本条が適用されることはありません。
ただし、特許権者は、特許権侵害により専用実施権の実施許諾料収入が減少した場合には、民法709条に基づく損害賠償請求ができると解されています。
「特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額」
事前に実施権設定契約を締結し実施料を支払っている場合と同額とすれば、予め実施許諾を求めるという動機が失われることになりかねません。
また、国有特許の実施料算定方式を採用したり、いわゆる業界相場に基づいて認定した場合には、侵害された特許権が有する固有の経済的価値が反映されないという不都合が生じます。
以上の事情を考慮し、「特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額」の認定にあたっては、特許権者が当該特許権の実施を許諾する方針を採用していたか否か、特許権者と侵害者との関係上実施権設定の可能性があったか否か、業界における特許発明の技術的優位性、特許発明に至るまでに特許権者が費やした時間・費用・労力、特許権者による過去の実施許諾実績、特許権者が特許発明の実施により得た利益、同種発明の実施許諾実績、侵害者の行為態様等を考慮すべきものと考えます。
「筋組織状こんにゃく事件判決」(大阪地裁平成14年10月29日判決)では、
「必ずしも当該特許権についての実施許諾契約における実施料率に基づかなければならない必然性はなく、そうした実際の実施許諾契約における実施料率や業界相場等も考慮に入れつつ、特許発明の技術内容や重要性、侵害の態様、侵害者が侵害行為によって得た利益、権利者と侵害者との競業関係や特許権者の営業政策等を総合考慮して、相当な実施料率を定めるべきである。」と判示され、「5相ステッピングモータの駆動方法事件判決(大阪地裁平成15年10月9日判決)では、「適法な取引関係を前提として約された実施料率は、円滑な取引関係の継続や販売の促進という種々の取引的要素を考慮して定められることも多いから、これをそのまま不当利得又は損害賠償の額に反映させるのは相当ではない。」と判示されています。
権利者が主張を行わない場合
特許権者は、一般的に、1項あるいは2項に基づき損害賠償請求項を行い、これらの主張が認められない場合の予備的主張として、特許権侵害により特許権者が被る損害の最下限ともいうべき3項を主張することになります。
それでは、特許権者が3項に基づく損害賠償請求を主張していない場合であっても、裁判所は、本項に基づく損害賠償を認めることができるかということが問題となります。
特許権に基づく損害賠償請求は、1項、2項、あるいは3項に基づくものであっても1個の不法行為に基づく損害賠償請求権であること、1項、2項、3項の各規定は損害額を推定する規定であり、損害額の認定は弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき相当な損額を認定することができる(民訴248条)ことから、特許権者が予備的に3項の主張を行っていない場合であっても、裁判所は3項に基づき損害額の認定をなし得ると考えます。
4項
4項前段は、3項において最小限度の損害賠償として実施料相当額の損害賠償も認めたことを受けて、3項所定の金額を超える損害賠償請求を妨げるものではないことを注意的に規定したものです。
4項後段は、民法709条、102条1項あるいは2項に基づき、3項所定の金額を超える損害賠償請求を行う場合に適用される規定であり、侵害者による侵害行為が軽過失に基づく場合には、かかる侵害者の事情を考慮して損害賠償額の算定することができると規定しています。特許権を侵害するか否かの判断は、微妙な判断を伴うものであり必ずしも容易ではありません。
ところが、特許発明の内容いかんによっては侵害者が巨額の賠償を強いられることもありえます。
そこで、裁判所において具体的な事案に応じた妥当な損害額の認定を行い得るえるように4項後段の規定が設けられました。
なお、侵害者に経過失が認められる場合であっても3項所定の金額を下回ることは許されないとされています。
製品の一部が特許権侵害となる場合
1項の損害賠償において、全体製品の一部が侵害特許権侵害にあたるときに全体製品販売価格に基づいて利益の額の算定を行った場合には、当該特許発明の全体製品に対する寄与率を考慮することになります。
前記「蓄熱材製造方法事件」判決では、全体製品に占める特許発明及び侵害製品の寄与度を考慮すべきとして、潜熱蓄熱式電気床暖房装置という性質上、蓄熱材が機構上も商品価値の構成上も必要不可欠な重要な要素であることは明らかである」として寄与率を60%と認定しました。
また、2項の損害賠償において、侵害者が製造・販売した製品の一部に特許発明が使用されている場合の特許権侵害による損害賠償は被告製品の販売によって被告が得た利益への寄与率に応じた損害額に推定が行われます。
「内視鏡洋フィルムカセット事件」判決(東京裁平成6年5月30日判決)では、フィルムが被告製品の製造原価に占める割合が相当に大きいこと、購入者が医療機関や医師であるところ、フィルム自体の品質、性能に着眼して被告製品を選択購入することも少なくないことを理由に、被告が得た利益への寄与率を2分の1とされました。
102条の適用を受けうる主体
専用実施権者は、特許権侵害者に対する差止請求権を有し(100条)、損害賠償請求権を有します(102条、103条、民709条)。
他方、通常実施権は、前記したとおり債権的権利であるところ、第三者による債権侵害が不法行為になることは判例においても認められているところです。
ただし、全ての債権侵害が不法行為となるわけではなく、
- 債権の帰属自体の侵害
- 債権の目的たる給付の侵害
- 債務不履行への加担
の3つの形態の債権侵害が損害賠償の対象になるとされています。
通常実施権は、重複して同様の実施権を設定することができるため、第三者によって特許権が侵害されたとしても、特許権者が第三者に加担しているという特殊の場合を除き、債権侵害には該当せず損害賠償請求を行うことができません。
東京地裁昭和36年11月20日判決(下民集12巻11号2808頁)、大阪地裁昭和59年4月29日判決(無体例州16巻1号271頁)、大阪高判昭和59年12月21日(無体例集16巻3号843頁)においても、通常実施権者の損害賠償請求が否定されています。
他方、完全独占通常実施権及び独占通常実施権においては、通常実施権者の権利の帰属自体を侵害しているといえるため、損害賠償請求を行うことができます。
「人工植毛用植毛器事件」判決(大阪地判昭和54年2月28日判決)、前掲大阪地裁昭和59年4月26日判決、「シアノグアニジン化合物製法事件」判決(東京地判平成10年10月12日判決)においても、独占的通常実施権者に損害賠償請求を認めています。